
コミュニケーション
チーム・組織づくり
マネジメント
管理職・経営人材
組織開発
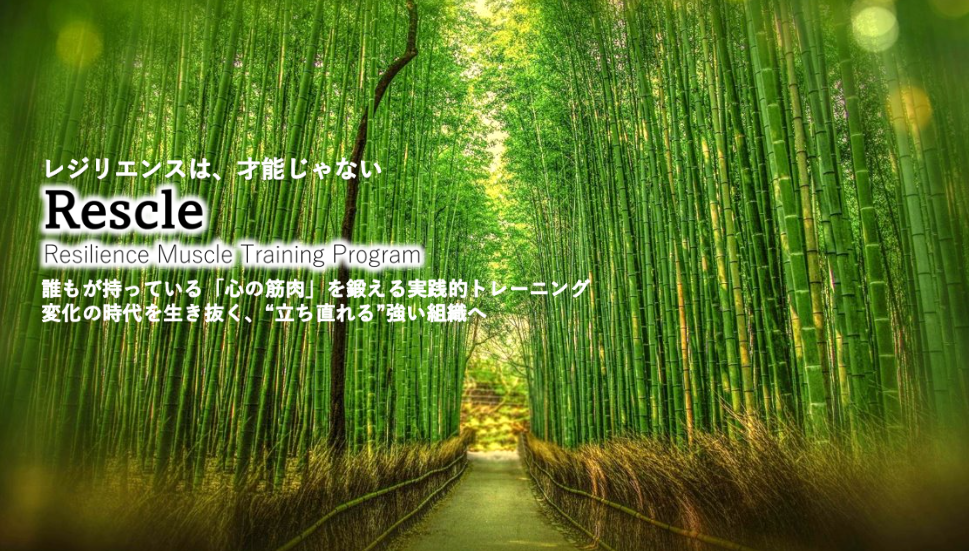
「心理的安全性」は、Google社が提唱した“生産性の高いチームに共通して見られる要素”であり、
成功するチームづくりにおいて欠かせない重要なポイントと言われています。
しかし…
そもそも、成果を出し続けるチームをつくるためには、
「最高の人財を集めるだけで良い結果出る」のでしょうか。
どんな優れた人財であっても、
「チーム内で個々が互いに相乗効果を発揮できる状態」でなければ、
成果を出すことはできないでしょう。
チーム内での相乗効果は、メンバー一人ひとりが、
自分の意見や気持ちを自由に表現できる環境があって、初めて生まれるものです。
「この業務について、上司に話してみよう」
「いま悩んでいるこの施策は、〇〇さんに相談したら解決の道筋が見えるかもしれない」
このように、「自分の意見や感情を安心して表現できる組織」であるということが、
成果を出し続けるチームの要素であるのです。
そして同時に「心理的安全性が高い組織」の状態ともいえるでしょう。

では、実際に組織においてどのような場面で、
「心理的安全性が低い」と感じることが多いのでしょうか?
ズバリ、心理的安全性が低い組織には、以下のような特徴があります。

そのため、心理的安全性が確保されていない職場では、
〇意見が言いづらい
〇自分がここにいても良いのか、自分の存在価値に不安を感じる
という状態に陥りやすくなります。
徐々にコミュニケーションが希薄になると信頼関係が構築しづらくなり、
最終的には休職・離職に繋がる可能性も高まります。
そのため、会社にとって「心理的安全性を確保すること」は、人材の確保や生産向上においても
重要な要素といえるでしょう。
では、実際に「心理的安全性が高い組織」を作るためにはどのようなことが必要なのでしょうか?
心理的安全性を考える上でよくいただくお悩みの一つに、
「緊張感がなく安心できる環境は良いが、組織として“厳しさ”も必要ではないか?」
「何でも許してしまうと、会社全体が緩くなり、結果的に悪影響を及ぼすのではないか?」
というお声をいただきます。
確かにこのままでは、いわゆる「ぬるま湯組織」になってしまう可能性があります。

心理的安全性が高い = 自分の意見や気持ちを安心して表現できる組織の状態
ぬるま湯組織 = 変化を恐れ、新しいアイデアや変革を受け入れにくい状態
ここで重要なのは、
「心理的安全性を確保することはぬるま湯組織を作ること」と同義ではないということです。
新しいことへ挑戦するとき、一歩を踏み出すのに勇気がいるものです。
「否定されるかもしれない」
「自分の意見は聞いてもらえないのではないか」
といった不安つきまとい、その結果新しい挑戦を避けてしまうことがあります。
このような環境では、「新しいことをする➡衝突することが怖い」 という考え方が根付いてしまい、
現状維持が優先される傾向が強まります。
一方で、心理的安全性が高い職場であれば、
新しい挑戦に対して、意見も率直に言いやすく、実行に移しやすい環境であることが多いです。
「この会社でまだまだ成長していきたい」
「自分を認めてくれるチームで、今後も働き続けよう」
このように一人ひとりの成長意欲が高まり、チーム・組織として目指す目的目標を目指しやすくなるのです。
つまり、
「心理的安全性が高い組織がぬるま湯組織になる」のではなく、
「心理的安全性が低いことが原因でぬるま湯組織が生まれる」と考えることができるでしょう。
では具体的に、どのように心理的安全性を確保していけばよいのでしょうか。
重要なキーワードは3つ、「承認」「透明性」「場の提供」です。

まず承認とは、
「相手に関心を持ち、理解しようという姿勢を持つこと」です。
相手に関心を持つことで、「相手を知ろう」「話してみよう」という行動が生まれてきます。
例えば、
「〇〇さんはどう考えるだろうか」
「〇〇さんはどんなことをやってきて、どのようなことをこれからしようと思っているのだろうか」
相手を理解しようという姿勢そのものが、相手の存在を「承認」することにつながるのではないでしょうか。
何か上司や先輩に相談をしたいと思ったとき、
相手がしっかり目を見て話をきいてくれると、安心して話せるものです。
作業をしながら横目で見るのではなく、しっかり自分の顔を見て話を聞いてくれる。
自分を知ろうという相手の姿勢に、「この人は私の話を聞いてくれる」「安心して話して良いんだ」と
感じた経験がある方も多いのではないでしょうか。
この「承認」においてもっとも大切なことは、「否定をしない」ということです。
コミュニケーションを取るうえで、
自分と違う意見に対して、反発の気持ちが出たり、違うなと感じてしまうことはあるかもしれません。
ただ重要なのは否定することではなく、「違う意見をまず受け止めること」です。
「この人は、こんな考え方をするんだ」
このように自分の意見を言う前に、相手の考え方を一度受け止めてみましょう。
次に透明性とは、
「なぜ」を説明すること、目的を明確にリクエストすることです。
管理職やリーダーの方は、組織やチームの方向性を決める機会が多くあると思います。
その際、役割分担や指示出し、といった何かを依頼する場合、
一方的に「これをやっておいて」と伝えるのではなく、
を一緒に伝えることが重要です。
指示を受けた側は、
納得した上で行動に移すことが出来ます。
そして、上司やリーダーに求められたレベル感で行動した結果、上司側も期待に応えてくれたことで
承認してもらいやすく、承認された部下も達成感を得られやすくなります。
明確に「なぜ」を伝えることで、チームや組織におけるモチベーション向上にも
つながっていくのではないでしょうか。
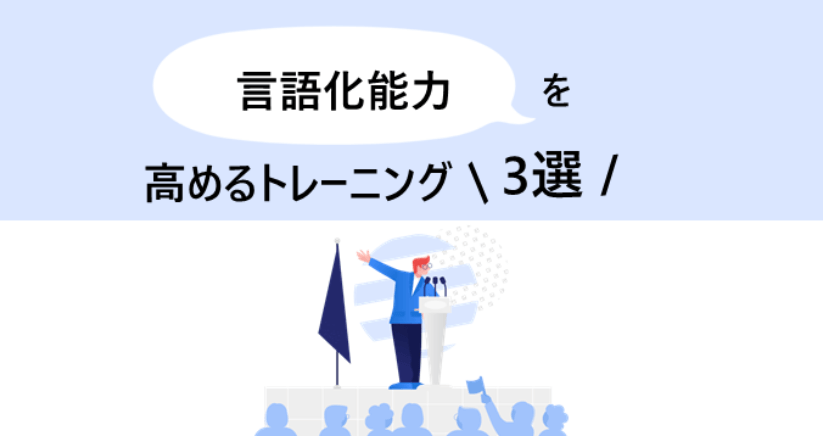
ポイントの3つ目は、「コミュニケーションの場を増やす」ことです。
コロナ禍以降、リモートワークやハイブリットでの働き方が増えた企業も多いと思います。
それに伴い、オフィスでの何気ないコミュニケーションが減少したと感じる方も多いのではないでしょうか。
朝出社した際の、「おはよう!昨日はありがとうね」といった声かけ。
ちょっとした雑談の中で生まれる気づきや信頼関係。
こうした小さなコミュケーションの積み重ねが減ったことを不安に思う方も多いはずです。
そのため、リモートワークでは、日々のちょっとした積み重ねで信頼関係を構築してきた時間を
「意図的に」作ることが重要です。
弊社FCEトレーニング・カンパニー事業本部では、朝礼・夕礼の時間で「日常会話の代わりになる場」を
作っています。
主に、「今日の目標を共有する」「業務のゴールを設定する」「お互いに感謝を伝えあう」
このようなことを行います。
「意図的に場を設ける」にあたり大事なことは、
事業本部長である私自身が朝礼を行う「理由」をしっかり伝え続けることだと思っています。
どんな目的で、どのようにその時間を過ごしてほしいのか、明確に伝えること。
すると徐々に意図的な時間が浸透していき、社員一人ひとりにとって当たり前の時間になっていきます。
リモートワーク環境であっても、お互いにコミュケーションをとることを大切にする組織風土に
つながっていると感じています。
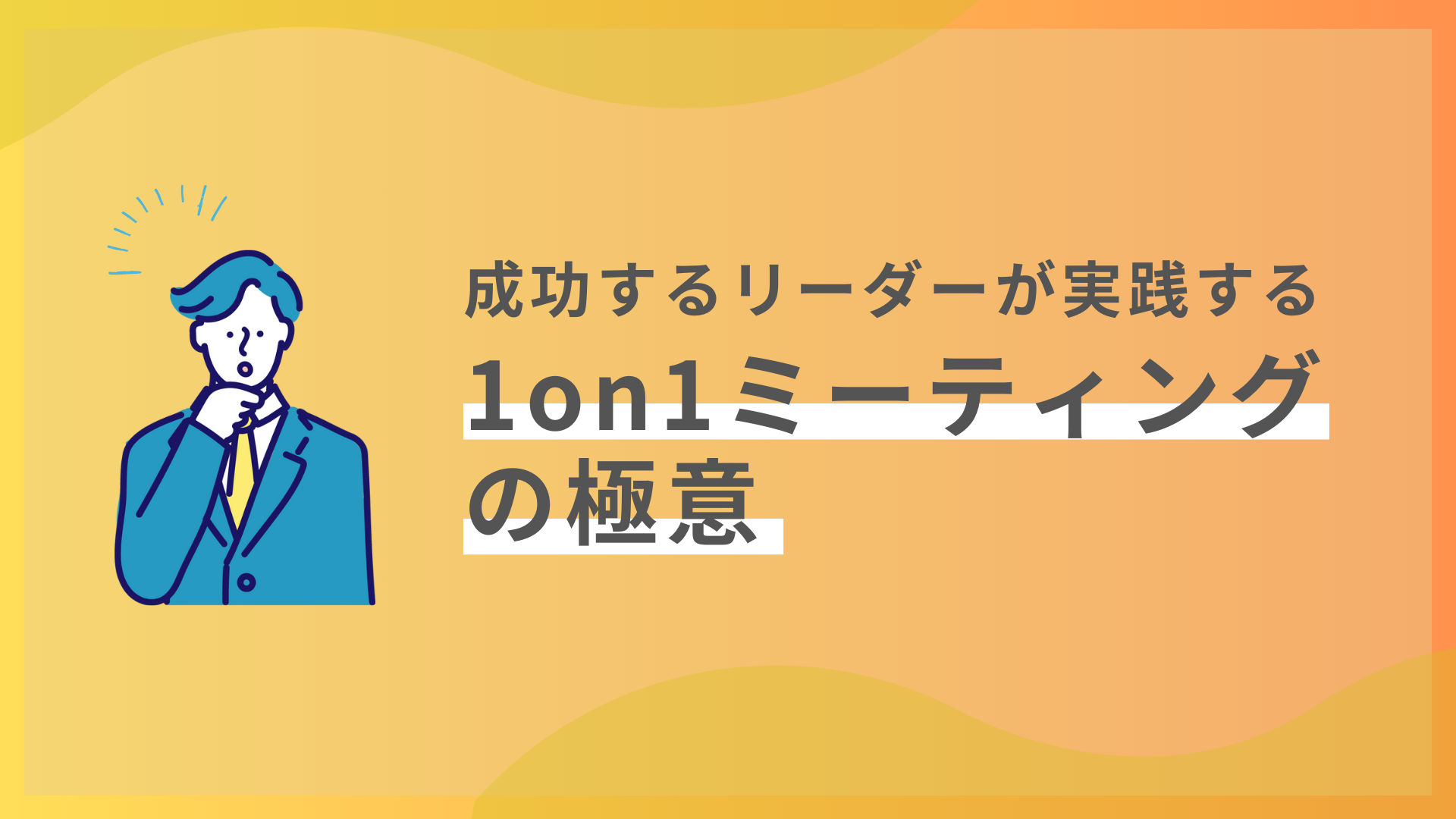
ここまで、心理的安全性を高めるポイントや環境づくりについてお伝えしました。
では、あなたのチームの心理的安全性は今、どのような状態でしょうか。
ここでは、チームの心理的安全性を簡単にチェックできるリストについて紹介します。
このテストでは、7つの質問に答えることで、チームの心理的安全性の高さを確認できます。
質問内容によって得点が大きい方が心理的安全性が高い・低いが分かれます。

チェックリストは、いかがでしたでしたか?
「ここは全然できていなかった…」「この点は、問題なさそう」など
7つの項目を通じて、どの分野で心理的安全性が高いのか・低いのか、
強化すべきポイントを把握できたのではないでしょうか。
そして、やってみて自分はどう感じたか。
結果を客観的に捉え、どの角度から取り組んでいけばよいかの指標になり、
取り組むべき優先順位を決める一方法として活用することができます。
心理的安全性が高い状態とは、「自分の意見や感情を安心して表現できる環境」です。
今までお伝えしてきた3つのポイントが重要になります。
①「承認」: お互いを理解し、関心を持つ
②「透明性」: 「なぜ?」を明確にし、情報をクリアにする
③「コミュニケーションの場を増やす」: 意図的にコミュケーションの機会を作る

そして最後に、何よりも重要なこととして、お互いの「心理的安全性」への理解が必要です。
チームはリーダーや管理職だけで作れるものではありません。
チームのメンバー一人ひとりが理解し、安心して働ける環境づくりに主体的に関わることが大切です。
ぜひ、今日からできることを始めてみましょう。

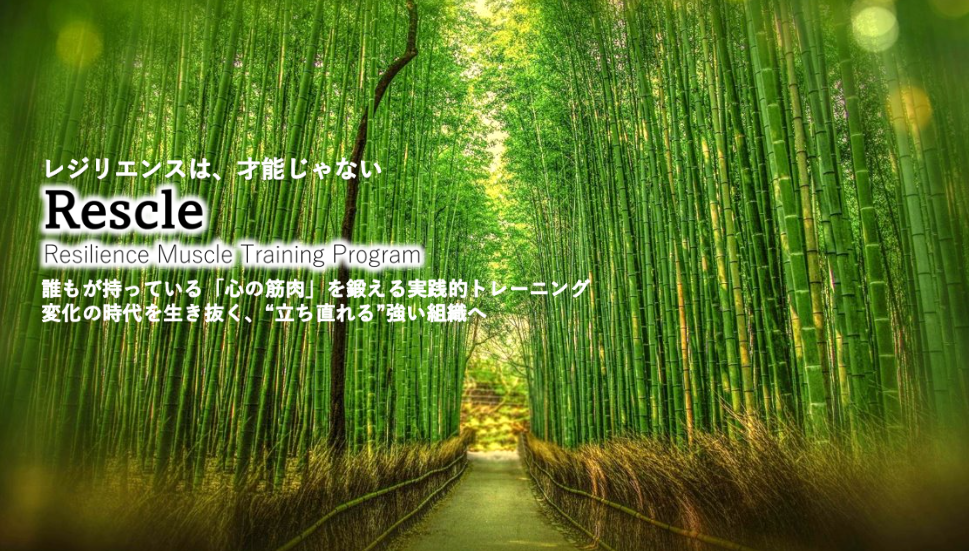








※対象カテゴリのうち、対象期間内(2021年7月1日〜2022年6月30日)に投稿された口コミが8件以上あり、各カテゴリで口コミの総得点が上位30%以上のサービス
※1〜※4 マーケティングリサーチ機構調べ 調査概要:(※1,※2)2022年4月期 (※3)2022年6月期 (※4)2022年7月期_ブランド名のイメージ調査

